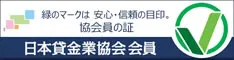- 0120-128-552 (受付時間 / 9:30~18:00)
- お申込み
- トップ
-

- 医療・介護業界の基礎知識
-

- 記事一覧
-

-
レセコンとは?電子カルテとの違い・連携や自院に合った選び方を解説
-
レセコンとは?電子カルテとの違い・連携や自院に合った選び方を解説
レセコンとは?電子カルテとの違い・連携や自院に合った選び方を解説
医療機関/クリニック/歯医者
公開日:

レセコン(レセプトコンピュータ)とは、レセプトを作成するコンピュータやシステムのことです。ほぼすべての医療機関や薬局が導入しており、毎月のレセプト業務の負担を軽減し、業務効率化を図るための重要な役割を担っています。
本記事では、レセコンの概要や電子カルテとの違い、導入によるメリットを解説します。レセコンを選ぶ際のポイントも紹介するので、導入を検討されている事業者さまはぜひ参考にしてください。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /

もくじ
「レセコン」とはレセプトを作成するシステム
レセコン(レセプトコンピュータ)とは、レセプト(診療報酬明細書)を作成するコンピュータやシステムのことで、「医事会計システム」とも呼ばれます。
社会保険診療報酬支払基金によると、2024年6月30日時点の普及率は96.9%と高く、多くの病院・診療所、歯科、薬局で導入されていることが分かります※。
特に、病院では普及率が高く、紙レセプトによる請求割合は0.3%と低い結果でした。
区分
電子レセプトによる請求割合
紙レセプトによる請求割合
病院(400床以上)
99.7%
0.3%
病院(400床未満)
99.7%
0.3%
診療所
97.6%
2.4%
歯科
93.3%
6.7%
調剤
99.3%
0.7%
全体
96.9%
3.1%
レセコンは、医療機関などが診療報酬を正確かつ迅速に請求するために欠かせないシステムです。
出典:社会保険診療報酬支払基金「請求状況(医療機関数・薬局数ベース)【令和6年5月診療分】」
レセプトとは
レセプトとは、医療機関などが保険者に対して医療費を請求するために発行する請求明細書のことです。
医療機関などが被保険者ごとに月単位で作成し、翌月10日までに支払基金(社会保険診療報酬支払基金)、国保連合会(国民健康保険団体連合会)に送付します。
レセプトの請求後に、支払基金、国保連合会で請求内容が適正かどうかの審査が行われ、支払額が確定します。
レセコンの主な機能
レセコンでは、主に以下のような機能が利用できます。
- 受付業務
- 診療内容の入力
- 請求内容のチェック
- 保険点数の自動算定
- レセプトの作成
- レセプトの請求
- 会計業務
- 患者に提供する文書の作成
- 他社システムとの連携
- 経営状況の分析
実際の機能はレセコンによって異なります。複数のレセコンを比較し、自院に合ったものを選びましょう。
レセコンと電子カルテの違い
「電子カルテ」とは、カルテをPCなどで作成し、データとして保存したものです。レセコンと電子カルテには、主に以下の違いがあります。
項目
レセコン
電子カルテ
目的
会計情報の管理
医療情報の管理
主な使用者
医療事務担当者
医師や看護師
診療報酬の請求業務を行うレセコンに対し、電子カルテは診療内容や診断結果、経過などの医療情報を管理するシステムです。
また、レセコンは主に医療事務担当者が使用しますが、電子カルテは医師や看護師などが使用します。
レセコンと電子カルテは連携が可能
レセコンと電子カルテは、使用する目的や使用者が異なりますが、連携することでさらなる業務効率化が図れます。
連携方法は、「一体型」と「連動型」の2つです。
一体型
レセコンと電子カルテのシステムが一体になったタイプ
連動型
レセコンと電子カルテのシステムが別々になったタイプ
それぞれ単体でも利用できますが、レセコンと電子カルテを連携すれば、受付から会計までを一元管理できます。
患者情報やカルテに入力したデータがレセプトに自動で反映されるため、業務量の大幅な軽減が見込めるでしょう。
レセコン導入によるメリット

前述の通り、レセコンは診療報酬の請求業務を正確かつ効率的に行うための重要なシステムです。導入によって主に以下のメリットが期待できます。
- 業務の効率化を図れる
- コストを削減できる
- 人為ミスを防げる
業務の効率化を図れる
レセコンでは、保険点数の算出やレセプト点検を自動化できます。診療内容を入力すると保険点数が自動で計算されるため、診療報酬の請求業務が大幅に効率化されます。
また、従来のようにレセプトを紙に出力することなく、レセコンを通じてオンライン請求できるため、印刷や仕分け作業も不要です。
電子カルテ一体型のレセコンなら、医師などが入力した内容がそのままレセプトとして反映されるため、さらなる効率化が図れます。受付や会計業務も効率化できるため、患者さんの待ち時間も短縮できるでしょう。
コストを削減できる
自動化によって業務が効率化すると、より少ない人数で請求業務を行えるようになり、人件費を削減できます。また、レセプトの出力が不要となるため、印刷コストの削減も見込めるでしょう。
ただし、レセコンの導入時には初期費用がかかるため、長期的な視点で検討することが大切です。
人為ミスを防げる
保険点数の算定やレセプト点検の自動化によって、人為ミスを防げることもメリットのひとつです。
自動チェック機能によって算定ミスや入力漏れを迅速に見つけ、指摘・訂正候補の提示をしてくれるため、修正もスムーズに行えます。レセコンによって機能は異なりますが、自動チェックされるのは主に以下のような項目です。
- 診療に関する基本情報が正しいか
- 算定可能回数を超えていないか
- 一定期間内に複数回算定できない診療行為がないか
- レセプト病名に誤りや漏れがないか
- 診療日に関する誤りがないか
また、クラウド型のレセコンは診療報酬の改定も自動で反映されるため、法令違反のリスクも防ぐことができます。
レセコンを選ぶ際のポイント
毎月、月末から月初にかけて集中的に行うレセプト業務は、医療機関にとって特に負担が大きい業務です。業務を円滑に進めるためには、自院に合ったものを選ぶことが重要です。
この章では、レセコンを選ぶときのポイントを解説します。
- オンプレミス型とクラウド型のどちらか
- 電子カルテとの連携は一体型と連動型のどちらか
- サポート体制が整っているか
- 操作しやすい仕様か
- コストはどれだけかかるか
オンプレミス型とクラウド型のどちらか
レセコンは、提供形態によってオンプレミス型とクラウド型の2つに区分されます。
オンプレミス型
院内に設置したサーバーと院内のコンピュータをローカルネットワークで接続して運用する形態
クラウド型
WEBを通じ、クラウド事業者が持つクラウドサーバーで運用する形態
オンプレミス型のレセコンは、院内のネットワークで完結するため情報漏洩のリスクが低く、セキュリティが高いことがメリットです。
いっぽうで、院内にサーバーを設置するため初期費用が高く、更新時にも費用がかかります。
クラウド型レセコンのメリットは、初期費用が比較的安く、場所を問わず利用できる点です。ただし、インターネット環境がなければ利用できず、インターネット回線や接続状況によっては反応が遅くなることもあります。
また、WEB上のサーバーを使用するため、安全に利用するには万全なセキュリティ対策が必要です。クラウド型レセコンを選ぶ際は、情報漏洩を防止するための対策や個人情報保護の取組みが十分かどうかをよく確認しましょう。
なお、メーカーによっては、障害発生時にクラウドサーバーに切り替えて利用できる「ハイブリッド型」のレセコンを提供しています。
電子カルテとの連携は一体型と連動型のどちらか
電子カルテとレセコンを連携する場合は、連携方法(一体型、連動型)にも着目しましょう。
一体型は、ひとつのシステムで受付から会計まで一元管理したい場合に適した連携方法です。それぞれのシステムで操作を覚える必要がないことに加え、問い合わせ先の窓口がひとつになるメリットもあります。
いっぽう、すでに電子カルテを導入しており、費用を抑えて新たにレセコンのみを導入したい場合は、システムが別々になっている連動型を検討するのもよいでしょう。
なお、メーカーによって連携できる電子カルテが異なるため、連動型を選ぶ際は連携が可能かどうかの確認が必要です。
サポート体制が整っているか
トラブル時に備え、手厚いサポートを提供しているレセコンを選ぶとあんしんです。具体的には、以下のようなポイントを確認しましょう。
- 電話やメールでのサポートだけでなく対面サポートが受けられるか
- WEBを通じた遠隔サポートが利用できるか
- 災害時のサポートがあるか
- 障害サポートの受付時間が自院の診療時間に対応しているか
操作の問い合わせ対応だけでなく、ネットワーク障害が起きた際に業務を継続できるか、迅速な復旧が可能かなどを確認することが大切です。
障害サポートの受付時間は、レセコンによって異なります。自院の診療時間に合ったサポートが受けられるメーカーを選びましょう。
操作しやすい仕様か
レセコンの操作性も重要な項目のひとつです。レセコンに不慣れな医療事務担当者でも、ストレスなく直感操作できるかどうかを確認しましょう。
- レイアウトが見やすいか
- 使用頻度の高い項目を登録できる機能があるか
- 操作に迷ったときのナビゲートがあるか
- 検索機能が充実しているか
なお、無料のデモンストレーションやセミナーで操作性を確かめられるメーカーもあるため、積極的に活用するとよいでしょう。
コストはどれだけかかるか
レセコンには、導入費用や導入後の維持費用がかかります。導入の目的を明確にしたうえで複数のメーカーを比較し、長期的な視点でコストをシミュレーションして検討しましょう。
オンプレミス型のレセコンは、院内にサーバーを設置するため、一般的にまとまった導入費用が必要です。
いっぽう、クラウド型のレセコンは導入費用がかからない、またはオンプレミス型と比べて低く、導入後は月額使用料を支払うことで利用できます。月額使用料に含まれる費用やオプションの料金・種類は、メーカーによってさまざまです。
別途導入支援費用やサポート費用などがかかる場合もあるため、内訳や内容をしっかり確認しましょう。
レセコンの導入・維持で資金が必要なら診療報酬担保ローンもご検討を
レセコンなどの機器の買い替えや電子化などに伴い、まとまった設備資金・運転資金が必要な事業者さまは、診療報酬担保ローンの利用もご検討ください。
AGメディカルでは、医療を営むお客さま向けに、診療報酬を担保にお借入れが可能な「診療報酬担保ローン」をご用意しています。
AGメディカルの診療報酬担保ローンでは、現在および将来の診療報酬を最大4.0ヶ月評価し、100万円から最高で10億円までのご融資が可能です※1。機器の購入資金だけでなく、増築や新施設開設にかかる費用、各種税金・社会保険料の支払いなど、幅広くご利用いただけます。
また、原則として保証人や不動産担保なしで利用でき※2、保証料・契約時手数料のご負担もありません※3。
お借入れをご検討の際は、「お借入れ1秒診断」をご利用ください。かんたんな項目の入力で、ご融資が可能かどうかを簡易的に診断できます※4。
所定の審査により融資額は変動します。
法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。
支払期日前に返済する場合(一部償還を含む)は、早期返済違約金をいただきます。
診断の結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。実際の審査では、当社規定によりご希望にそえない場合もありますのでご了承ください。
まとめ
レセコンとは、レセプトを作成するためのコンピュータやシステムです。診療報酬の迅速・正確な請求に欠かせないシステムであり、現在、ほとんどの医療機関で導入されています。
自院に合ったレセコンを選べば、医療事務担当者の負担が軽減されるだけでなく、人件費の削減や患者さんの待ち時間の短縮などにもつながります。また、電子カルテと連携することで、さらなる業務効率化が可能です。
レセコンを選ぶ際は、初期費用だけでなく、長期的な視点でコストをシミュレーションしましょう。設備投資などでまとまった資金が必要な事業者さまは、診療報酬担保ローンの利用もご検討ください。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /