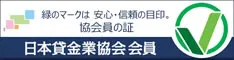- 0120-128-552 (受付時間 / 9:30~18:00)
- お申込み
- トップ
-

- 医療・介護業界の基礎知識
-

- 記事一覧
-

-
介護報酬の仕組みとは?単位や単価の計算方法をわかりやすく解説!
-
介護報酬の仕組みとは?単位や単価の計算方法をわかりやすく解説!
介護報酬の仕組みとは?単位や単価の計算方法をわかりやすく解説!
介護施設/訪問介護
公開日:

介護事業を安定的に運営するためには、「介護報酬」の仕組みを正確に理解しておく必要があります。報酬単位の計算方法や加算・減算の要件、3年に一度行われる報酬改定は、経営計画や職員の処遇改善に大きく関わる重要な要素です。
本記事では、介護報酬の基本的な仕組みから単位・単価の計算方法まで、介護事業者が知っておくべき内容をわかりやすく解説します。適切な報酬体系の理解により、事業運営の安定化と質の高いサービス提供を実現しましょう。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /

もくじ
介護報酬の仕組み

介護報酬とは、介護事業者が利用者(要介護者または要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に対して支払われる報酬です。介護報酬は、介護事業者にとって運営基盤となっています。
介護報酬は、介護サービスの種類ごとにサービス内容・要介護度、事業所・施設の所在地などに応じた平均的な費用が算出されています。
この基準額は、介護保険法に基づき、厚生労働大臣が介護給付費分科会の意見を踏まえて決定するもので、公定価格として位置づけられています。
介護サービス料のうち、1割から3割は利用者の自己負担で、残りの7割から9割は介護保険から支払われる介護報酬として処理されます。この仕組みにより、利用者の負担を軽減しながら、適切なサービス提供が可能です。
なお、介護報酬請求の流れは以下のとおりです。
- 利用者と契約する
- サービスを提供する
- 国民健康保険団体連合会に介護報酬を請求する
- 利用者へ利用者負担分の費用を請求する
- 国民健康保険団体連合会から介護報酬が支払われる
サービス提供から介護報酬が支払われるまでには約2ヶ月程度の期間がかかるため、事業者は資金繰りを考慮した運営計画を立てる必要があります。
この支払いサイクルを理解し、適切なキャッシュフロー管理をおこなうことが、安定した事業運営の基盤となります。
介護報酬は「単位」で計算する
介護報酬の計算方法を理解するには、「単位」「単価」「加算」という3つの基本的な概念を押さえることが重要です。介護報酬の算定は、「サービスごとに定められた単位数×1単位あたりの単価」で計算します。
単位制度の採用により、地域間の格差を調整し、多様なサービス内容に応じた柔軟な報酬設定が可能となりました。
さらに、加算制度によってサービスの質向上や専門性の高いケアに対するインセンティブが設けられており、事業者の経営努力が報酬に反映される仕組みです。
単位と単価
介護報酬の「単位」とは、介護保険制度において介護サービスの報酬額を計算するための基準となる点数のことです。
この単位は提供されるサービスの種類や内容、利用者の要介護度、サービス提供時間、施設の種別などによって国が細かく定めています。
事業者にとっては、単位数を正確に把握し適切に請求することが、収益性を向上させるうえで欠かせません。
1単位の単価は基本的に10円ですが、地域ごとの物価や人件費の違いを調整するため、10円~最大11.40円まで幅があります。
これは地域区分制度と呼ばれる仕組みで、地域やサービスごとに人件費や物価が異なることを考慮し、地域間で不公平が生じないように調整しています。
地域区分やサービス種別ごとに「上乗せ割合」「人件費割合」が設定されており、これらを掛け合わせて1単位の単価が決まる仕組みです。
たとえば、東京都心部では人件費や賃料が高いため、同じサービスでも運営コストが高くなります。地域区分制度によって、こうした地域ごとの特性が反映され、全国で均質なサービスの提供が実現されています。
サービス別地域単価表
地域区分は1級地から7級地(その他)まで分類されており、それぞれ異なる上乗せ率が適用されます。
人件費割合
1級地(20%)
2級地(16%)
3級地(15%)
4級地(12%)
5級地(10%)
6級地(6%)
7級地(3%)
その他(0%)
70%
11.40円
11.12円
11.05円
10.84円
10.70円
10.42円
10.21円
10円
55%
11.10円
10.88円
10.83円
10.66円
10.55円
10.33円
10.17円
10円
45%
10.90円
10.72円
10.68円
10.54円
10.45円
10.27円
10.14円
10円
最も高い1級地(東京都特別区)では上乗せ率が最大となり、その他の地域では基本単価の10円が適用されます。
地域区分の見直しは定期的に行われており、各自治体の実情に応じた適切な区分設定が維持されています。事業者は該当する地域区分を正確に把握し、適切な単価で請求することが重要です。
加算と減算
「加算」は、専門性の高い対応や手厚い人員配置、あるいは特別なサービス体制を提供した際に、通常の基本報酬に加えて支給される項目です。
加算を算定することで、事業所の収入を増やすとともに、サービスの質向上を図れます。
代表的な加算には、処遇改善加算、ベースアップ等支援加算、サービス提供体制強化加算などがあり、いずれも職員の処遇改善や専門性の強化を目的としています。
最近では、ICT化の推進や科学的介護の導入、感染症対策の強化といった社会の変化に対応する新たな加算も登場しています。介護事業者は、これらの動向を常に把握しておくことが重要です。
いっぽうで、「減算」はサービス提供に必要な運営基準・人員基準等に不備があった場合に、基本報酬から差し引かれる項目です。
人員配置基準未達や業務継続計画未策定、高齢者虐待防止措置未実施などは、いずれも減算対象となるため、法令を確実に順守することが求められます。
サービスごとの介護報酬単位一覧

介護報酬は提供するサービスの種類によって大きく異なります。ここでは主要な介護サービスごとの報酬単位について詳しく解説します。
各サービスの特性や提供内容に応じて、適切な報酬体系が設定されているため、事業者はこれらの単位を正確に把握して請求を行いましょう。
訪問介護
訪問介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問して身体介護や生活援助を提供するサービスです。報酬単位は提供時間やサービス内容などによって設定されており、身体介護では20分未満から90分以上まで細かく区分されています。
サービス内容
時間区分・条件
単位数
身体介護
20分未満
163単位
身体介護
20分以上30分未満
244単位
身体介護
30分以上1時間未満
387単位
身体介護
1時間以上1時間30分未満
567単位
身体介護
(以降30分ごとに追加)
+82単位
生活援助
20分以上45分未満
179単位
生活援助
45分以上
220単位
通院等乗降介助
1回あたり
97単位
身体介護+生活援助
所要時間20分から起算し25分ごと
+65単位(195単位まで)
出典:独立行政法人 福祉医療機構「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年4月施行版)」
同一建物等居住者に対するサービス提供では、効率化を考慮した減算が適用されます。いっぽうで、中山間地域等での訪問では特別地域加算が設けられており、地域特性に応じた柔軟な運営が可能です。
通所介護
通所介護(デイサービス)は、利用者が施設に通って入浴、食事、機能訓練などのサービスを受ける制度です。報酬単位は利用時間と要介護度、事業所の規模によって細かく設定されています。
なお、通常規模型通所介護の単位は以下のとおりです。
サービス時間
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
3時間以上4時間未満
370
423
479
533
588
4時間以上5時間未満
388
444
502
560
617
5時間以上6時間未満
570
673
777
880
984
6時間以上7時間未満
584
689
796
901
1,008
7時間以上8時間未満
658
777
900
1,023
1,148
8時間以上9時間未満
669
791
915
1,041
1,168
出典:独立行政法人 福祉医療機構「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年4月施行版)」
大規模型事業所や超大規模型事業所では、スケールメリットを考慮した減算が適用されます。いっぽうで、中山間地域等の小規模事業所では加算が設けられており、地域特性に応じた運営が可能となっています。
個別機能訓練加算や栄養改善加算、口腔機能向上加算などの自立支援に向けた専門的なケアに対する加算も充実しており、質の高いサービス提供が評価される仕組みです。
訪問看護
訪問看護は、看護師等が利用者の居宅を訪問して療養上の世話や診療補助をおこなうサービスです。医療的ケアが中心となるため、他のサービスと比較して高い単位設定となっています。
サービス時間
訪問看護ステーション
病院・診療所
20分未満
314単位
266単位
30分未満
471単位
399単位
30分以上1時間未満
823単位
574単位
1時間以上1時間30分未満
1,128単位
844単位
出典:独立行政法人 福祉医療機構「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年6月・8月施行版)」
緊急時訪問看護加算や特別管理加算などの各種加算により、専門性の高いケアに対する適切な評価が行われています。
24時間対応体制加算や看護・介護職員連携強化加算など、在宅生活を支える体制づくりに対する加算も設けられており、地域包括ケアシステムの推進を後押しする仕組みとなっています。
短期入所生活介護
短期入所生活介護(ショートステイ)は、利用者が短期間施設に入所して介護サービスを受ける制度です。家族の介護負担軽減や緊急時の受け入れなど、重要な役割を担っています。
要介護度
単独型・従来型個室
併設型・従来型個室
単独型・ユニット型個室
併設型・ユニット型個室
要支援1
479単位
451単位
561単位
529単位
要支援2
596単位
561単位
681単位
656単位
要介護1
645単位
603単位
746単位
704単位
要介護2
715単位
672単位
815単位
772単位
要介護3
787単位
745単位
891単位
847単位
要介護4
856単位
815単位
959単位
918単位
要介護5
926単位
884単位
1,028単位
987単位
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について【短期入所生活介護】」
夜勤職員配置加算や看護体制加算、栄養マネジメント加算など、サービスの質向上に向けた各種加算が設けられています。利用者のニーズに応じた、多様なケアの提供が評価される仕組みといえるでしょう。
連続利用日数による減算制度もあり、適切な利用期間での運用が求められています。また、療養食加算や入所前後訪問指導加算など、きめ細かなケアに対する評価も充実しています。
居宅介護支援
居宅介護支援は、ケアマネジャーが利用者のケアプランを作成し、サービス調整をおこなう重要な役割を担っています。要介護度別に月額単位で報酬が設定されており、継続的なケアマネジメントが評価される仕組みです。
【居宅介護支援費(Ⅰ)】
区分
対象件数範囲
要介護1・2
要介護3・4・5
(ⅰ)
45件未満
1,086単位
1,411単位
(ⅱ)
45~60件未満の部分
544単位
704単位
(ⅲ)
60件以上の部分
326単位
422単位
出典:独立行政法人 福祉医療機構「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年4月施行版)」
【居宅介護支援費(Ⅱ)】
区分
対象件数範囲
要介護1・2
要介護3・4・5
(ⅰ)
50件未満
1,086単位
1,411単位
(ⅱ)
50~60件未満の部分
527単位
683単位
(ⅲ)
60件以上の部分
316単位
410単位
出典:独立行政法人 福祉医療機構「介護給付費単位数等サービスコード表(令和6年4月施行版)」
初回加算や入院時情報連携加算、退院・退所加算など、きめ細かなケアマネジメントに対する各種加算が設けられています。
特定事業所加算では、質の高いケアマネジメントを実施する事業所に対してⅠからⅢまでの段階的な加算が適用され、専門性向上への取組みが適切に評価されます。
また、AI活用や多職種連携の推進など、最新技術や手法を活用したケアマネジメントに対する加算も新設されました。業務の効率化や提供するサービスの質を向上させるために、IT化やICT化を進めていきましょう。
具体的な計算例
介護報酬の仕組みを理解するために、実際のサービス提供を想定した具体的な計算例を見てみましょう。地域区分や加算・減算を含めた実践的な計算方法を解説します。
【利用者の状況】
- 利用者:要介護3
- サービス内容:身体介護1時間30分(訪問介護)
- 事業所所在地:東京都渋谷区(1級地、人件費割合70%)
- 初回加算:あり
- 緊急時訪問介護加算:あり
項目
内容
基本報酬
身体介護1時間 :387単位
身体介護30分追加:180単位
基本報酬合計:567単位
加算
初回加算:200単位
緊急時訪問介護加算:100単位
合計:300単位
総単位数
567単位+300単位=867単位
地域単価の適用
1級地(人件費割合70%):11.40円/単位
介護報酬総額:867単位×11.40円=9,883円
利用者負担額(1割負担の場合)
9,883円×10%=988円
介護保険支払額
9,883円×90%=8,894円
上表はあくまでも一例です。提供する介護サービスや地域区分、加算・減算の組み合わせにより、同じサービスでも最終的な報酬額が大きく変わります。
介護報酬の改定は3年ごと
介護報酬は3年ごとに時代のニーズや物価の変動、社会情勢などを踏まえて改定されます。この定期的な見直しにより、適切なサービス提供体制の維持と質の向上が図られているのです。
2024年の介護報酬改定では、改定率が「+1.59%」となっており、全体的にプラス改定となりました。この改定では、処遇改善やサービスの質向上、効率的なサービス提供体制の構築などが重点課題として位置づけられています。
どのようなサービスを提供したかによって加算され、逆に所定の基準を満たさなければ減算もあるため、事業者は常に最新の基準を把握しておく必要があります。
介護事業所の運営者は、最新の介護報酬を把握したうえで、世の中に求められているサービスや政府が介護事業所に求めている内容を理解することが重要です。
特に、昨今はICT化の推進や業務効率化、人材確保・定着に向けた取組みなどが評価される傾向にあります。事業者は、政府が求めている内容を踏まえた経営戦略の策定が必要です。
科学的介護の推進やデータ活用による介護サービスの質の向上も重要なテーマとなっており、従来の経験や勘に頼った運営から、エビデンスに基づいた科学的なアプローチへの転換が期待されています。
介護施設の資金調達はAGメディカルの「介護報酬担保ローン」のご利用を
介護報酬が入金されるのは、実際に介護サービスを提供した月から起算して翌々月の20日~月末日頃になります。このようにサービスの提供から入金までにタイムラグがあるため、その間の資金繰りで困ってしまう場面があるかもしれません。
AGメディカルの「介護報酬担保ローン」は、国民健康保険団体連合会(国保)に対して有する債権を担保に融資を行っており、最大で介護給付費の4.0ヶ月分の資金を調達できます(※1)。
100万円~最高10億円まで借入れでき(※1)(詳細はこちら)、運転資金だけでなく事業投資にも活用できます。ファクタリングをご利用中・赤字決算でもご検討可能で、保証料・契約時手数料は不要(※2)、保証人・不動産担保も原則不要です(※3)。
興味がある方は、ぜひホームページの「お借入れ1秒診断」を活用して、資金調達の可能性を確認してみましょう。
適切な資金繰りにより、質の高いサービス提供と事業の持続的成長を実現できます。介護事業の特性を理解した専門的な融資サービスとして、ご活用ください。
所定の審査により融資額は変動します。また、審査結果によっては融資できない場合があります。
支払期日前に返済する場合(一部償還を含む)は、早期返済違約金をいただきます。
法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。
まとめ
介護施設の経営者は、経営の安定とサービスの質向上のためにも、介護報酬の最新情報を知っておくべきです。介護報酬は事業者の主な収入源であり、報酬改定による単価の変更や加算の新設・廃止は、経営収支に大きな影響を与えるためです。
介護職員の処遇改善加算やベースアップ等支援加算の内容は、人材確保や職員の定着に直結します。人手不足が深刻化する介護業界において、優秀な人材を確保するためにも、最新の報酬情報を把握することが大切です。
単位や単価の計算方法、地域区分による差異、各種加算・減算の要件など、複雑な仕組みを正確に理解することで、適切な報酬請求と経営計画の立案が可能となります。3年ごとの報酬改定にも適切に対応し、持続可能な事業運営を実現しましょう。
資金繰りにお困りの方は、AGメディカルの「介護報酬担保ローン」の利用をご検討ください。適切な資金調達により、安定した事業運営と質の高いサービス提供の両立が可能となります。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /