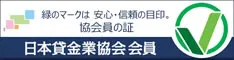- 0120-128-552 (受付時間 / 9:30~18:00)
- お申込み
- トップ
-

- 医療・介護業界の基礎知識
-

- 記事一覧
-

-
訪問介護業界が抱える課題とは?なくなるといわれる理由も解説
-
訪問介護業界が抱える課題とは?なくなるといわれる理由も解説
訪問介護業界が抱える課題とは?なくなるといわれる理由も解説
医療機関/クリニック/歯医者
公開日:

訪問介護業界は高齢化社会の進展とともに需要が拡大しているいっぽうで、深刻な課題を多数抱えています。
具体的には、小規模事業所が多いことによる競争激化や従業員の高齢化、慢性的な人手不足などが挙げられます。これらの問題が複雑に絡み合い、事業所の経営を圧迫しているのが現状です。
状況を放置していると、訪問介護の経営はどんどん悪化してしまうでしょう。本記事では、訪問介護事業所が直面している課題の詳細と、安定経営のために取組むべき対策について、具体的なデータと専門的な視点から解説します。
訪問介護業界の現状理解と今後の展望を把握し、事業所として打つべき対策を考えてみましょう。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /
訪問介護はなくなる?現状の課題を確認

結論、訪問介護事業の需要がなくなることはないでしょう。高齢化が進む日本において、在宅での介護サービスは今後も重要な役割を担い続けるからです。
しかし、現状ではさまざまな課題を抱えており、これらの問題が解決されなければ継続困難な事業所が増加する可能性があります。
事業所の小規模化
訪問介護事業所の多くは小規模であり、2024年時点で介護サービス従事者数が9人以下の事業所は27.2%を占めています(※)。
訪問介護事業所は初期設備投資が比較的少額で済むことから、参入障壁が低く、競争が激しくなりやすい業界です。
特に規模の小さい事業所では、利用者のニーズをひとつの施設で全て満たすのが難しく、複数の訪問介護事業所を併用するケースが増えています。
このような状況は、ケアプランを作成するケアマネジャーにとっても、事業所間の連絡や調整業務の負担増加につながるでしょう。
実際に、他の事業所も併用している利用者が1名以上いる訪問介護事業所は全体の57.2%を占めており、これが長時間労働や就業環境の悪化の一因となっています。
小規模事業所では、管理者が現場業務と経営業務を兼務するケースが多く、戦略的な経営判断に十分な時間を割けない問題も見逃せません。
また、職員が急に欠勤したり退職したりした場合の代替要員の確保が難しく、サービス提供の継続にも課題があります。
出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」
従業員の高齢化と慢性的な人手不足
訪問介護員の平均年齢は54.4歳と高く、65歳以上の職員が24.4%を占めるなど、職員の高齢化が深刻な問題となっています(※1)。
加齢に伴う体力の低下などを理由に退職したり、シフトに入る時間や回数を減らしたりする職員が増加しており、サービス提供に支障が生じている状況です。
人手不足の深刻さは、有効求人倍率にも表れています。2023年度時点で施設介護員の有効求人倍率が3.24倍であるのに対し、訪問介護員は14.14倍と非常に高い水準です(※2)。
この数値は、求職者1人あたり約14件の求人があることを意味し、深刻な人材不足を裏付けています。
介護業界そのものが人手不足に直面しており、運営基準を満たせない事業所は閉鎖を余儀なくされるケースもあります。
これは単に人員不足の問題にとどまらず、業界全体の持続可能性に関わる重要な課題といえるでしょう。
さらに、人手不足により1人あたりの業務負担が増加し、職員のストレスや疲労が蓄積しやすい環境となっています。このような状況が離職を招き、人手不足の悪循環を生んでいるのが現状です。
出典:厚生労働省「訪問介護」
資格必須化による人材採用の難しさ
訪問介護は基本的に1人で利用者宅を訪問するサービス形態であり、介護職員初任者研修またはその上位の資格が求められることから、人材採用のハードルが高くなっています。
この資格がなければ「身体介助」と「生活援助」といった基本的な介護サービスを提供できません。
さらに、介護職員初任者研修は約130時間の受講が必要であり、一定の費用もかかるため、他業界に比べて応募者が少なく、採用活動の難易度が上昇しています。
特に介護業界未経験者にとっては、資格取得の負担が参入の障壁となり、人材確保の妨げとなっています。事業所側も資格取得支援制度の導入などを検討する必要がありますが、小規模事業所では費用面の負担が大きいという課題も抱えています。
さらに、資格を持っていても実務経験が浅い場合は、即戦力として活躍できるまでに時間がかかります。採用や教育にかかるコスト、研修体制の整備なども事業所の大きな負担となっているのが現状です。
基本介護報酬の引き下げ
介護報酬はサービス提供後すぐには支払われず、入金までに約2ヶ月かかるのが一般的です。その間も職員の給料や施設の家賃といった固定費は発生するため、特に小規模な事業所では資金繰りに悩まされるケースが多くなっています。
さらに、2024年の介護報酬改定では、身体介護(20分未満)で1.2%、生活援助(20分以上45分未満)で0.8%の基本報酬が引き下げられ、事業所の経営環境はより厳しくなりました。
特に加算が算定しにくい小規模な事業所では、基本報酬の引き下げの影響が大きく、経営が困難になるケースが増加しています。
加算制度は事業所の質向上を促す仕組みですが、人員や設備の制約により加算要件を満たせない小規模事業所にとっては不利な状況です。
この報酬体系の変更により、事業所間の格差が拡大し、小規模事業所の淘汰が進む可能性が高まっています。事業所は加算の積極的な取得や効率的な運営体制の構築など、さまざまな対応が求められているのが実情です。
報酬引き下げの背景には、国の社会保障費抑制政策があります。今後も厳しい改定が続く可能性があるため、事業所は従来以上に効率的な経営を意識しなければなりません。
安定経営のために訪問介護事業所が取組むべきこと

訪問介護事業所はさまざまな課題に直面していますが、事業を維持し成長させるには、具体的な対策が必要です。複数の対策を組み合わせて総合的に取組むことで、より大きな効果を期待できます。
事業所規模の拡大・統合を検討する
先述したように、訪問介護事業所の多くは小規模であるため、そこから生じる問題も少なくありません。こうした問題を解消する手段として、事業所の規模拡大や他事業所との統合は有効な選択肢となります。
事業を安定して継続するためには、利用者数90人・月商350万円がひとつの基準とされますが、実際にこの基準を満たしている事業所はごく一部にとどまっているのが実情です。
訪問介護事業所同士の統合により、人材不足の緩和・業務効率の向上・経営の安定化などが期待できます。統合により人員配置の最適化が可能となり、職員の労働負担軽減にもつながるでしょう。
また、規模拡大により加算要件を満たしやすくなり、収益向上も見込めます。ただし、統合には法的手続きや組織文化の統一など、さまざまな課題もあるため、専門家のサポートを受けながら慎重に進める必要があるでしょう。
統合の際は、サービス提供エリアの重複や職員の処遇統一、システムの統合など、具体的な課題への対応策も事前に検討しておくことが重要です。
ICT(情報通信技術)を活用する
ICT(情報通信技術)の活用により、利用者情報の管理やサービス提供記録の管理、介護報酬請求業務の効率化が実現できます。また、職員間や他事業所との利用者情報共有もスムーズになり、連携体制の強化につながります。
業務効率化による労働時間の短縮は就労環境の改善をもたらし、より質の高い介護サービスの提供により利用者満足度の向上も期待できるでしょう。具体的には、以下のような対策が効果的です。
- タブレット端末を活用したサービス記録の電子化
- AIを活用したシフト管理システム
- クラウドベースの情報共有システムの導入
ICT導入には初期投資が必要ですが、国の補助金制度も活用できるため、積極的な検討が推奨されます。ただし、高齢の職員が多い訪問介護業界では、操作の簡便性や研修体制の充実が欠かせません。
導入時は段階的な実施や職員への十分な研修期間の確保、操作に不安のある職員へのサポート体制構築なども重要です。
人材の確保と定着を強化する
介護業界の慢性的な人手不足に対応するため、人材の確保と定着の強化は不可欠です。人手が不足していると、利用者が満足できるサービスを提供できません。
採用手法を多様化するための手段は以下のとおりです。
- 利用する求人媒体の増加
- ハローワークへの積極的な掲載
- 求人イベントへの参加
なお、求人掲載やイベント参加の際には、求職者に仕事の魅力を効果的に伝える必要があります。
また、労働環境の改善も重要な要素です。柔軟な労働時間制度の導入や専門性向上、キャリアアップの機会提供、福利厚生の充実などが効果的な施策となります。
特に、訪問介護は移動時間や待機時間が発生しやすいため、これらに対する適正な評価と処遇改善が求められます。従業員がやりがいを持ち、あんしんして長く働ける環境整備を進めましょう。
また、職員のメンタルヘルス対策や職場内コミュニケーションの改善も定着率向上に寄与します。定期的な面談や研修機会の提供、職員同士の交流促進など、働きがいのある職場づくりが欠かせません。
近年注目される外国人材活用については、技能実習制度や特定技能制度の活用が可能です。
ただし、日本語能力の確保、文化的配慮、適切な受け入れ体制の整備が必要不可欠です。EPA(経済連携協定)による外国人介護福祉士候補者の受入れも選択肢のひとつですが、国家試験合格までの支援体制構築が求められます。
訪問介護の専門性を発信する
さまざまな介護サービスがある中で、訪問介護サービスの専門性に対する認知度は低い状況にあります。他の福祉系訪問サービスとの差別化を図りつつ、訪問介護の専門性を事業所内外に積極的に発信しましょう。
訪問介護の専門性には、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)の向上支援、多職種連携におけるゲートキーパー機能、利用者や家族との直接的な関わりによる生活支援などがあります。
これらの価値を具体的な事例とともに発信することが重要です。
潜在的な利用者やその家族に対して、「訪問介護を利用すれば、自宅にいながら自分らしい生活を送れる」という印象を与えることで、サービスの価値向上と需要拡大につながります。
ホームページやSNS、地域のイベントなどを活用した情報発信が効果的です。
地域包括支援センターや医療機関との連携強化も、専門性の認知向上と利用者紹介の増加に寄与する重要な取組みといえるでしょう。
加算の取得をめざす
最新の介護報酬改定を把握しつつ、さまざまな加算の取得をめざすことで収益向上が期待できます。
「居宅介護支援における特定事業所加算」「介護予防支援における加算」「訪問介護における特定事業所加算の見直し」などの制度変更を適切に活用しましょう。
2024年度(令和6年度)介護報酬改定では基本報酬引き下げが実施されたいっぽうで、質の高いサービスを提供する事業所への評価は手厚くなっています。
従来の基本報酬中心の経営モデルから、専門性の高いサービス提供と積極的な加算取得による収益確保モデルへの転換をめざしましょう。
加算取得のためには、要件を満たすための体制整備や書類作成などの準備が欠かせません。専門家の支援を受けることで、効率的に体制を整えることが可能です。収益が増加すれば、人材への投資や設備面の強化にも資金を回すことが可能になります。
加算制度は定期的に見直されるため、最新の情報収集と対応策の検討を継続的におこなう体制づくりも重要です。
訪問介護事業所の資金調達はAGメディカルの「介護報酬担保ローン」のご利用を
介護報酬が入金されるのは、実際に介護サービスを提供した月から起算して翌々月の20日~月末日頃となるため、サービス提供から入金までに約2ヶ月のタイムラグが発生します。この期間の資金繰りが課題となる事業所も少なくありません。
資金繰りにお困りの方は、AGメディカルの「介護報酬担保ローン」の利用をご検討ください。
AGメディカルの「介護報酬担保ローン」は、国民健康保険団体連合会(国保)に対して有する債権を担保とした融資制度です。最大で介護給付費の4.0ヶ月分の資金調達が可能で、100万円から最高10億円まで借入れできます(※1)(詳細はこちら)。
この制度は運転資金だけでなく事業投資にも活用でき、ファクタリングを利用中や赤字決算の事業所でも検討可能です。
また、保証料・契約時手数料は不要(※2)で、保証人や不動産担保も原則不要です(※3)。
所定の審査により融資額は変動します。また、審査結果によっては融資できない場合があります。
支払期日前に返済する場合(一部償還を含む)は、早期返済違約金をいただきます。
法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。
まとめ
訪問介護業界は参入障壁が低く小規模事業所が多い関係で、利用者の確保が困難な状況にあります。従業員の高齢化と慢性的な人手不足、基本介護報酬の引き下げなど、複数の課題が同時に発生している厳しい経営環境です。
これらの課題に対応するためには、必要に応じて事業所規模の拡大・統合やICT技術の活用を検討することが重要です。また、人材の確保と定着強化、専門性の積極的な発信、加算の確実な取得など、総合的な取組みが求められます。
最新の介護報酬改定にも注目し、得られる加算を確実に取得しながら、中長期的な視点で事業運営の安定化を図りましょう。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /