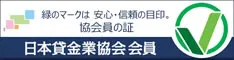- 0120-128-552 (受付時間 / 9:30~18:00)
- お申込み
- トップ
-

- 医療・介護業界の基礎知識
-

- 記事一覧
-

-
赤字の病院が増えている理由とは?黒字化させるためのポイントを詳しく解説!
-
赤字の病院が増えている理由とは?黒字化させるためのポイントを詳しく解説!
赤字の病院が増えている理由とは?黒字化させるためのポイントを詳しく解説!
医療機関/クリニック/歯医者
公開日:

コロナ補助金の終了や病床利用率の低下などの影響もあり、赤字経営の病院が増えています。赤字の状況が継続すると経営が持続不可能となり、閉院を余儀なくされるでしょう。
病院経営者の方は、持続可能な経営を実現するためにも、「なぜ赤字の病院が増えているのか」「経営状況を改善させるために、必要な取組みは何か」を考え、実践することが大切です。
この記事では、赤字の病院が増えている理由や、病院経営を黒字化させるためのポイントなどを解説します。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /
6割以上の病院が赤字の状況
一般社団法人日本病院会が発表した「2024年度診療報酬改定後の病院経営状況」によると、2023年は医業利益が赤字の病院が64.8%、経常利益が赤字の病院が50.8%でした。
2024年には赤字割合がさらに悪化し、医業利益の赤字割合は69.0%、経常利益の赤字割合は61.2%に上昇しています。

出典:一般社団法人日本病院会「2024年度診療報酬改定後の病院経営状況」
病院経営の赤字化は非常に深刻な問題であり、現状を放置すれば、地域の医療体制が維持できなくなる可能性もあります。
多くの病院が赤字になっている理由
病院経営の赤字化が増加している背景には、さまざまな要因が絡み合っています。
以下で、赤字経営の病院が増えている理由について、具体的に解説します。
コロナ補助金の終了
「コロナ補助金(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)」とは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けた病院や、医療提供体制の拡充や感染拡大防止を進めた病院に対して支給された補助金です。
コロナ補助金は、医療機関の「医業外収益」として計上されます。ここ数年は経常利益率が医業利益率を上回る傾向が続いていましたが、2023年5月に新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」へ移行したことを受け、コロナ補助金は縮小・終了しました。
その結果、医業外収益が減少することで経常利益率が低下し、赤字に転落する病院が増加しています。
また、「2024 年度病院経営定期調査」によると、2023年度の一般病床における100床あたりの医業利益は、補助金などを含めた場合、2億3,483万円の赤字でした。
いっぽう、補助金などを除いた場合の損益差額は1億9,826万円の赤字であり、補助金により赤字幅が一定程度緩和されていたことがうかがえます。
人件費・委託費など経費の増加
多くの医療機関では、診療報酬収入以上に経費が増加し、収支が悪化する傾向が続いています。
「2024年度診療報酬改定後の病院経営状況」によると、2023年度から2024年度にかけて、経費は増加しました。
項目
2023年度から2024年度の上昇率
材料費
2.0%
給与費
2.8%
委託費
4.2%
設備関係費
1.8%
研究開発費
2.7%
経費(水道光熱費など)
3.1%
出典:一般社団法人日本病院会「2024年度診療報酬改定後の病院経営状況」
しかしながら、物価や光熱費の上昇、人件費の高騰を、診療報酬の増加幅では補填しきれていないため、経営を圧迫しています。
特に、医療分野は人手不足の状況であり、人手を確保するために相応の待遇を用意する必要があります。
2024年の診療報酬改定で医療従事者の賃上げを目的とした「ベースアップ評価料」という加算が新設されましたが、人件費増加分を十分にカバーできていません。
人件費の負担増が病院の経営赤字につながっている要因のひとつといえるでしょう。
病床利用率の低下
患者数の減少に加え、医療技術の進歩や各病院による早期退院の取組みによる在院日数の減少を背景に、病床利用率は低下傾向にあります。
独立行政法人福祉医療機構によると、2023年度の平均在院日数は17.7日で、2019年度の18.2日から0.5日短縮されました(※)。
入院患者数の減少が続くことで、入院診療による収益が減少するため、医療機関にとっては経営が赤字化する一因となっています。
出典:独立行政法人福祉医療機構「2023 年度 病院の経営状況について」
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /
病院経営を黒字化させるためのポイント

病院経営を黒字化させるためには、「収入を増やす」「経費を減らす」という2つの面からアプローチする必要があります。
病院の経営者として行うべきことを見ていきましょう。
経営状況の問題・課題点を把握する
まずは、経営状況の問題・課題点を正確に把握する必要があります。病院が抱える経営上の問題を数値として可視化し、具体的に改善すべきポイントを明らかにしましょう。
たとえば、経費が適正である場合は、収入を増やすための取組みが必要となります。いっぽうで、収入が平均水準と比較して遜色がないにもかかわらず赤字の場合は、何かしらの経費が負担となっている可能性があります。
なお、病院経営において、必ず確認すべき財務指標は以下のとおりです。
項目
計算式
医業収支比率
医業収益÷医業費用×100
人件費比率
人件費÷医業収益×100
材料費比率
材料費÷医業収益×100
病床稼働率
1日平均入院患者数÷病床数×100
具体的な数値に基づいて分析を行うことで、影響度の高い課題から優先的に対応できるため、短期間での効果が期待できます。
外来・入院別の患者数の推移や、患者1人あたりの単価推移などを分析し、定量データと定性データの両面から検証してください。
人件費の適正化を図る
病院経営において、人件費は医療収益の約50%程度を占めるともいわれています。経費のなかでも特に大きな割合を占めるため、適正な人員配置を行い、人件費を見直すことで、病院経営の健全性を高めることが可能です。
具体的に、人件費の適正化を図るための取組みは以下のとおりです。
- 時間帯別・曜日別の需要変動に合わせたシフト設計をする
- 診療科別・時間帯別の患者数に応じた柔軟な人員配置をする
- 夜勤・当直体制を見直し、時間外労働の削減を図る
- 各部署の業務フローを洗い出し、無駄な業務を削減する
- ICTツール(電子カルテ、勤怠管理システムなど)の導入による業務効率化を図る
人件費の削減を意識するあまり、人員不足になってしまうと、1人あたりの業務量が過重になってしまいます。医療の質の低下を招いてしまうため、単にスタッフを減らすのではなく、適正な人員配置を意識することが大切です。
あわせて、ICTの活用による業務効率化を実現できれば、勤務時間を抑えられます。スタッフの勤務時間が減れば人件費を抑えられるため、ICTの活用も積極的に検討しましょう。
コスト削減を徹底する
一連のコストは病院の収益を圧迫する要因となるため、さまざまな観点から経費削減に取組むことが重要です。
たとえば、医薬品・診療材料費の仕入れに関しては、購買方法の見直しや、共同購入・一括購入を導入することで、仕入れコストを削減できる可能性があります。
また、在庫管理や使用量の適正化を徹底することも効果的です。在庫管理が不十分な状態では、過剰な仕入れによって無駄なコストが発生してしまうため、早急に見直しが必要です。
清掃・給食・医事課業務などコア業務以外については、アウトソーシングの活用も有効な選択肢のひとつです。「病院内で雇用する場合」と「アウトソーシングする場合」の費用を比較し、よりコストを抑えられる方法を選択しましょう。
既にアウトソーシングをしている場合は、委託契約の見直しや委託先の変更により経費を削減できる可能性があります。
さらに、照明のLED化や高効率空調機器への交換をすることにより、光熱費を削減できます。
設備投資をする際には初期費用が発生しますが、長期的に見ればコスト削減によるメリットが初期投資を上回る可能性があります。そのため、老朽化した設備は交換を検討することが重要です。
感染症対策を強化する
コロナ禍においては、医療機関でも混乱が発生し、来院者が不安を感じることも少なくなかったでしょう。未曽有の出来事であったため、対応に苦慮した医療機関もあったのではないでしょうか。
今後も、同じように感染症による混乱が発生する可能性が考えられます。あんしんして来院できる環境を整備するためにも、病院内で感染症対策を強化するとよいでしょう。
具体的には、感染症患者の動線確保や院内の衛生管理の徹底などが挙げられます。また、新しい感染症以外にも、感染力の強いウイルス(インフルエンザやノロウイルスなど)の患者が来院したとき、待合室を分ける対策も効果的です。
来院者の満足度を高めて増患・増益をめざす
病院が収益を上げるためには、患者の獲得が欠かせません。病院の収入源である診療報酬を安定的に得るためにも、患者や家族があんしんして利用できる病院を作ることが大切です。
たとえば、スタッフ全員に医療接遇を徹底することにより来院者の満足度を高められ、継続して利用してもらえるでしょう。また、以下のように病院の利便性を高めることも効果的です。
- WEB上で予約できるシステムを導入して待ち時間を短縮する
- 早朝・夜間診療を導入する
- オンライン問診を導入する
- 待合室の環境改善を図る
- 清潔感のある院内環境を維持する
- プライバシーに配慮した診察室や待合スペースを設ける
特に近年は、医療機関を選ぶ際に評判や口コミを確認する人が少なくありません。よい評判や口コミを獲得し、その内容が広がれば、新規来院者を獲得できる可能性が高まります。
診療報酬の加算を適切に計上する
病院収入を増やしていくには、診療報酬加算の正確な計上も大切なポイントです。
2024年度の診療報酬改定では、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)」「医療DX推進体制整備加算」「高齢者施設等感染対策向上加算」などの新たな加算項目が創設されました。
これらの改定内容から、政府が医療機関に対して、医療DXの推進による業務の効率化や、地域包括ケアシステムのさらなる推進を求めていることがわかります。賃金改善やDX化に取組んだ際には、これらの加算を漏れなく計上することが重要です。
なお、診療報酬は原則として2年ごとに改定されており、次回は2026年度に予定されています。常に最新の情報を確認し、対応できる体制を整えておきましょう。
離職率を下げ人材定着を促進する
離職率を下げ、人材定着を促進することにより、採用や教育に関連するコストを抑えられます。新規でスタッフを雇用する際には、以下のようなコストが発生し、病院の経営を圧迫することが少なくありません。
コスト
詳細
直接的な採用コスト
・求人広告費
・人材紹介会社への手数料
・採用担当者の人件費
・面接・選考にかかる費用(機会損失)
教育・研修コスト
・新人研修費用
・OJT期間中の指導者の人件費
・研修資料・教材費に関する事務的コスト
生産性低下によるコスト
・一人前になるまでの期間生産性低下
・指導者の業務負担増による生産性低下
・一時的なチーム全体における業務効率の低下
つまり、離職率を下げるために「スタッフが働きやすい環境を作ること」も、病院経営者にとって重要な業務のひとつといえるでしょう。
経験豊富なスタッフが長期的に定着することにより、継続的で質の高い医療提供が可能となります。その結果、業務の効率化が進み、労働時間の短縮にもつながり、さらに働きやすい環境になる好循環を生み出せます。
離職率を下げ、人材の定着を促進するためには、働きやすい環境づくりや福利厚生の充実といった対策が効果的です。具体的には、以下のような取組みが考えられます。
- 勤務体制の最適化
- 給与・評価制度の見直し
- ワークライフバランスの推進
- ハラスメントが発生しない体制の整備
- 年次有給休暇の取得促進
- 育児・介護支援制度の充実
- 明確なキャリアパスの提示
- メンター制度の導入
長く働いてもらうためには、モチベーションの維持や向上が欠かせません。定期的なキャリア面談や、キャリアアップを支援するための取組みも検討するとよいでしょう。
補助金や助成金を活用する
補助金や助成金は返済不要の資金であり、病院経営において大きな支援となります。雑収入として計上されるため、資金繰りの改善にも役立ちます。
たとえば、人材採用や設備投資を行った際に、国や自治体から補助金・助成金を受けられるケースがあります。医療機関で利用できる可能性がある制度を一部ご紹介します。
助成金・補助金
内容
人材開発助成金「人材育成支援コース」
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練や厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化をめざす訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部について助成を受けられる
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
60歳以上の人、母子家庭の母、就職氷河期世代の人などを採用したとき、助成を受けられる
IT補助金
業務効率化やDXに向けた ITツール(ソフトウェア、サービスなど)を導入したとき、経費の一部について補助を受けられる
省エネルギー投資促進支援事業費補助金
高効率空調や業務用給湯器などをはじめとした15種類の設備を更新したとき、経費の一部について補助を受けられる
補助金や助成金を受給できれば、実質的に設備投資や人材採用、人材育成に関するコストを削減できます。
また、IT補助金や省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、人件費の抑制や光熱費の抑制といった、継続的なコスト削減効果をもたらしてくれるでしょう。
資金調達にお困りならAGメディカルの「診療報酬担保ローン」がおすすめ
多くの病院が赤字経営の状態にあるため、実際に資金繰りで頭を悩ませている病院経営者の方もいるのではないでしょうか。経営改善のための資金が必要な場合は、AGメディカルの「診療報酬担保ローン」をご検討ください。
AGメディカルの「診療報酬担保ローン」は、国民健康保険団体連合会(国保)や社会保険診療報酬支払基金(社保)に対して有する債権を担保にして、融資を受けられるサービスです。
100万円から最高10億円までのご融資(詳細はこちら)に対応しており、大規模な設備投資にも柔軟に対応できます(※1)。
ファクタリングをご利用中・赤字決算でも相談可能で、保証人・不動産担保は原則不要です(※2)(※3)。運転資金だけでなく、税金や社会保険料の支払いなど、さまざまな支払いで利用できるため、ぜひご相談ください。
所定の審査により融資額は変動します。また、審査結果によっては融資できない場合があります。
支払期日前に返済する場合(一部償還を含む)は、早期返済違約金をいただきます。
法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。
まとめ
一般社団法人日本病院会の資料によると、6割以上の病院が赤字です。コロナ補助金の終了や病床利用率の低下などの影響を受け、赤字の病院が増えているため、病院経営者の方は資金繰りに意識を払う重要性が高まっています。
現在の経営状況を確認し、もし解決すべき課題や問題点があれば、早急に手を打ちましょう。特に、昨今はさまざまなモノやサービスの価格が上昇しているため、今後も一連のコストが収益を圧迫する可能性が考えられます。
「収入を増やす」「支出を減らす」という両面で見直しを行い、赤字からの脱却だけでなく、黒字の拡大をめざしましょう。
資金繰りに困った際は、AGメディカルの「診療報酬担保ローン」をご検討ください。お電話やメールにて無料でご相談いただけます。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /