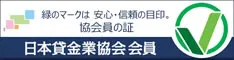- 0120-128-552 (受付時間 / 9:30~18:00)
- お申込み
- トップ
-

- 医療・介護業界の基礎知識
-

- 記事一覧
-

-
医療接遇とは?病院経営者が知っておくべきメリットや取組み方を解説
-
医療接遇とは?病院経営者が知っておくべきメリットや取組み方を解説
医療接遇とは?病院経営者が知っておくべきメリットや取組み方を解説
医療機関/クリニック/歯医者
公開日:

医療機関としての評判を高く保つためには、医師や看護師などをはじめ、勤務している全員が「医療接遇」を意識する必要があります。
医療機関へ足を運ぶ患者や家族は、多かれ少なかれ、不安や疑問を抱えています。医療従事者として患者があんしんできる適切な医療を提供するためには、医療接遇の理解は欠かせません。
今回は、医療機関において医療接遇を意識すべき理由やメリット、医療接遇の質を向上させるための取組みなどを解説します。患者があんしんして受診できる医療機関を整え、評判を高めていきましょう。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /

もくじ
病院経営者と医療従事者が知っておくべき医療接遇とは
医療接遇とは、医療機関において患者と接する際の態度や言葉遣い、行動などの対応全般を指す言葉です。患者だけでなく、その家族への心くばりや配慮も、医療接遇に含まれます。
医療機関には、心身に何らかの不調を抱えた患者が来院します。適切な医療方針を決定するためには、コミュニケーションを通じて、患者の抱える問題を正確に把握することが大切です。
具体的に、医療従事者が意識すべき医療接遇は以下のとおりです。
- 敬語を適切に使用する
- 患者の立場に配慮した説明を行う
- 専門用語を使わず、患者や家族が理解できるように伝える
- プライバシーに配慮する
- 患者の尊厳を守る態度を示す
- 治療や検査の内容を丁寧に説明する
- 共感的な態度を示す
- 傾聴する
- 不安を軽減する声かけを行う
医療接遇の徹底により質の高い医療サービスを提供でき、患者の満足度や医療機関への信頼構築につながります。
接客マナーと医療接遇の違い
一般的なサービス業における接客マナーと医療接遇では、以下のような違いがあります。
項目
一般的な接客マナー
医療接遇
対象者の状態
健康な状態の顧客が中心
体調不良や不安を抱えた患者が中心
目的
商品やサービスの販売・提供
治療・ケアの提供と患者の不安軽減
プライバシー配慮
基本的な個人情報保護
医療情報を含む高度なプライバシー保護
言葉づかい
丁寧語・敬語の使用
医療用語の適切な説明と丁寧語の併用
身体的距離
一定の社会的距離を保つ
診察や治療時に身体接触が必要な場合がある
待遇時の配慮
快適性と効率性を重視
患者の体調や心理状態を最優先
専門性の程度
サービスや商品知識が中心
医療知識とコミュニケーション能力の両立
環境への配慮
清潔で快適な空間づくり
感染予防を含む衛生管理と安全性確保
接客マナーは、主に自社の商品やサービスをアピールし、購入してもらうことが目的です。明るく礼儀正しく接しつつ、時には効率性を重視する場合があります。
いっぽうで、医療接遇では礼儀正しさだけでなく、患者の心身の状態に配慮した特別な対応が求められます。医療現場特有の倫理観や専門知識を持ちつつ、患者の不安や緊張に寄りそい、患者があんしんできるような温かい対応を行うことが大切です。
医療接遇では、マニュアルに従って動くよりも、患者状況に応じた接遇が求められます。「どのような困りごとがあるのか」「どのような配慮を行えばあんしんできるのか」を素早く考え、主体的に動く必要があります。
医療接遇を意識すべき理由
患者があんしんできる環境を整備するためには、医療現場全体で医療接遇を徹底することが必要不可欠です。患者離れが発生してしまうと、医療機関の運営に支障が出る事態になりかねません。
以下で、医療機関が医療接遇を意識すべき理由を具体的に解説します。
患者の不安やストレスを軽減するため
医療機関を受診する患者は、心身に何らかの不調を抱えています。不安やストレスがあり、普段よりも感情的になる可能性も高く、ちょっとした接遇の差で、クレームに発展する恐れがあります。
東京都の「令和5年度「患者の声相談窓口」実績報告」によると、相談者からの苦情内容として1番多かった内容は、「コミュニケーションに関すること」でした。
内容
割合
コミュニケーションに関すること
39.8%
医療行為、医療内容
19.9%
その他
10.1%
医療費
7.2%
診療拒否
4.8%
出典:東京都保険医薬局「令和5年度「患者の声相談窓口」実績報告」上位5位を抜粋
医療接遇により、患者の不安やストレスを軽減できれば、クレームを未然に防げるだけでなく、患者からの信頼を得ることで次回の来院につながります。
医療事故を予防するため
接遇意識が高いことで、丁寧なコミュニケーションを通じて患者のわずかな状態変化にも気づきやすくなり、医療事故の予防につながります。
また、医療機関は、「インフォームド・コンセント」に努めなければなりません。インフォームド・コンセントとは、患者に対して医療行為に関する十分な説明を行い、患者がそれを理解したうえで同意または拒否の意思を表明することです。
医療接遇が行き届いていることで、患者は医療従事者に対してあんしん感と信頼を持ちやすくなり、説明内容の理解も深まります。その結果、インフォームド・コンセントがより円滑に行われ、患者中心の医療が実現しやすくなります。
医療機関は、患者の健康を守るという医療の根本的な使命を果たすのはもちろん、重大な健康被害や後遺症を防がなければなりません。
医療接遇を徹底することにより、コミュニケーションの齟齬(そご)による誤解やミスを防止し、患者に適した医療・看護を提供できるでしょう。
職場のチームワークを強化するため
医療接遇を意識することで、職場内において相手を慮り、尊重する姿勢が自然と生まれます。その結果、職場内のスタッフ間でもコミュニケーションが活発になり、職場のチームワークを強化につながるでしょう。
医療現場では、患者の健康状態や服薬状況などのセンシティブな情報を取扱います。医師・看護師・技師・事務職など、多様な職種が協働する医療現場において、職場内における助け合いやスムーズな情報共有は欠かせません。
職種内の連携が強化され、より包括的な医療サービスを提供できるでしょう。良好なコミュニケーションは緊急時の患者対応の連携力を高め、組織的レジリエンスの向上にもつながります。
医療機関としての評判を向上させるため
患者やその家族に「あんしんして話せる」「頼りになる医療機関」という印象を持ってもらえれば、患者満足度の向上につながります。医療接遇を実践・向上させることは、医療機関の評判を高めるためにも効果的です。
病院やクリニック、薬局などは地域医療において重要な役割を担っています。医療機関の評判をよくすることで、患者が適切な医療を受けやすくなり、より地域医療へ貢献できるでしょう。
特に、昨今はWEB上の口コミサイトやSNSの普及により、患者の体験談が広まりやすい傾向にあります。
医療機関での対応に不備があると、ネガティブな評価が広まり、新規患者から敬遠される可能性も否定できません。いっぽうで、接遇の評判がよければ「初診でもあんしんできる」と感じてもらいやすくなり、来院のきっかけにもつながります。
医療技術だけでなく、スタッフ一人ひとりの接遇も医療機関の印象や信頼度に直結します。ほかの医療機関との差別化を図り、「口コミを参考にして受診先を選ぼう」といった患者ニーズにこたえるためにも、医療接遇の向上は重要です。
医療接遇の向上によって得られる経営上のメリット

先述したように、医療接遇を実践し、さらに向上させることで、来院者の増加や職場環境の改善など、さまざまなメリットが得られます。
医療機関の経営状況を改善させ、生産性を向上させるためにも、職場全体で医療接遇の意識を持つことが大切です。
増患・増益による利益率の向上
医療接遇の向上は、病院経営の収益性にも影響します。医療機関の主な収入は保険診療によるものであるため、医療機関としての評判を高めて来院者数を増やすことにより、増患・増益による利益率の向上が期待できます。
特に、複数の診療科がある場合、ひとつの診療科でのよい体験が、同院内の他科受診につながる可能性もあります。「この医療機関は親切」と思ってもらえるように、常に医療接遇の向上に意識を向けましょう。
クレームの減少と生産性の向上
医療接遇を向上させれば、来院者のあんしんや満足につながるため、自然とクレームが減少します。クレーム対応の時間が減少することで、重要な業務にリソースを割けるようになり、生産性が向上するでしょう。
また、クレーム対応はスタッフにとって心身ともに大きな負担です。クレーム対応の時間を減らすことにより、対応職員の精神的負担とストレスを軽減でき、働きやすい職場を実現できるでしょう。
その結果、サービスの質が向上してさらに満足度が上昇し、クレームが減少する好循環を生み出せます。時間をかけてでも、何らかの悩みや不安を抱えている患者に寄りそうことは、長期的に見ればメリットにつながります。
労働時間短縮による職場環境の改善
クレームの減少と生産性の向上により、労働時間を短縮できます。また、患者とのコミュニケーションが円滑化すれば、問診や説明の時間が効率化され、診療全体の流れがスムーズになるでしょう。
さらに、スタッフ一人ひとりが自身の業務に集中できれば、残業時間の削減にもつながります。生産性の高い業務により多くのリソースを割けるようになり、業務効率の向上とともに、職場環境の改善も期待できるでしょう。
また、経営者にとっても、労働時間を短縮し不要な残業を抑制することは、割増賃金の支出を抑えることにつながります。人件費の最適化という観点からも、医療接遇の徹底と向上は経営上の大きなメリットとなります。
優れた人材の定着
クレームが少なく、あんしんして働ける職場であれば、スタッフ全体の満足度は高まりやすくなります。その結果、優秀な人材が離職しにくくなり、医療機関としての高い生産性を持続することが可能です。
さらに、職場内のコミュニケーションが活発で、信頼関係を築きやすい環境であれば、人間関係のストレスによる離職を防ぐことにもつながります。思いやりのあるスタッフが多い職場ほど、自然と働きやすい環境が生まれ、人材の採用や定着を促進できます。
また、優れた人材の定着は、採用コストや教育コストの削減にも効果を発揮します。結果として人件費の最適化につながり、医療機関の経営にとっても大きなプラスとなるでしょう。
医療接遇を向上させるための意識や取組み
職場全体で医療接遇を向上させるためには、どのような点を意識し、どのような取組みを行うべきでしょうか。
ここでは、スタッフ全員が医療接遇を高め、医療機関全体の信頼性を向上させるために必要な意識や具体的な取組みについて解説します。
傾聴し患者の不安に寄りそう
「傾聴」とは、相手の話を耳だけでなく心でも受け止め、共感しながら相手の気持ちや考えを理解しようとすることです。
話し手が「この人は自分の話を理解しようとしてくれている」「不安に共感してくれている」と感じることで、あんしん感を得られます。
傾聴を意識し、相手の立場に立って話を聞くことで、相手は話しやすくなり、双方の理解が深まります。その結果、患者や家族の真のニーズや懸念をくみ取りやすくなり、より適切な治療方針の決定につながるでしょう。
傾聴を実践するコツは、相手の話を遮らずに最後まで聞くことです。加えて、話を聞くときは相手に目線を合わせたり、適度にうなずいて共感を示したりすることも効果的です。
また、患者や家族へ質問するときは、「はい・いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンよりも、自由に答えてもらえるオープンクエスチョンを使いましょう。こうした質問によって、相手の本音や潜在的な不安を引き出すことができます。
病院内で「接遇マナーの5原則」を徹底する
医療機関内では、以下の「接遇マナーの5原則」を徹底しましょう。
内容
詳細
あいさつ
・明るく元気な声で挨拶する
・相手の目を見て笑顔で対応する
・「おはようございます」「お大事になさってください」など、場面に応じた適切な言葉を選ぶ
表情(笑顔)
・自然で温かみのある笑顔を心がける
・口角を上げ、目も笑う「目の笑顔」を意識する
・状況に応じて表情を使い分ける
・マスク着用時でも目元で笑顔を表現する
身だしなみ
・清潔感のある服装と髪型を意識する
・制服は正しく着用し、しわや汚れに注意する
・爪は短く清潔に、派手なアクセサリーは避ける
・医療現場にふさわしい衛生的な身だしなみを意識する
言葉遣い
・丁寧語・敬語を正しく使用する
・専門用語は避け、わかりやすい言葉で説明する
・声のトーンや話すスピードにも配慮する
態度(姿勢・動作)
・背筋を伸ばしてよい姿勢を心がける
・歩き方や物の受け渡しを丁寧に行う
接遇マナーの5原則を徹底することで、来院した患者や家族にあんしん感を与え、「困ったときに頼れる存在である」と思ってもらえます。医療機関で働くすべてのスタッフがこの5原則の徹底を意識し、相手に配慮した言動を実践しましょう。
外部講師を招いて接遇研修や勉強会を開催する
内部でマナーを正しく伝えられる講師がいない場合や体制的に厳しい場合、医療接遇に詳しい外部講師を招く方法があります。専門家による医療接遇研修・勉強会を開催することで、スタッフ全員の理解を深められるでしょう。
接遇技術に加えて、医療コミュニケーションや心理学的な知見を持つ講師であれば、患者の視点に立った実践的なアドバイスを提供してくれます。
また、座学だけでなく、ロールプレイやグループワークを取り入れた研修は、実践的なスキルを効果的に習得するうえで非常に有意義です。
従業員の経験年数に応じて、異なる内容の研修を開催することも検討しましょう。たとえば、新卒や若手従業員向けの内容であれば、基本的な応対マナーや言葉遣いなどを盛り込んだ内容が考えられます。
中級者以上向けであれば、困難な場面での対応やクレーム対応など、より専門的な内容を盛り込むと実践的な知識やノウハウを習得できます。
医療機関が資金調達するときはAGメディカルの「診療報酬担保ローン」を
医療機関を経営していると、一時的に運転資金が不足することも考えられます。
資金不足にお悩みの方は、AGメディカルの「診療報酬担保ローン」をご検討ください。
「診療報酬担保ローン」は、国民健康保険団体連合会(国保)や社会保険診療報酬支払基金(社保)に対して有する債権を担保に、最大診療報酬請求額の4.0ヶ月分の資金を調達いただくことができます。
100万円から最高10億円の融資に対応(※1)(詳細はこちら)しており、調達したお金は運転資金だけでなく各種税金・社会保険料のお支払にもご利用いただけます。
保証料・契約時手数料は不要で、保証人・不動産担保も原則不要です(※2)(※3)。また、ファクタリングを利用中または赤字決算中でも検討可能です。
WEBサイト上に「お借入れ1秒診断」や「ご返済シミュレーション(※4)」などのツールをご用意しています。ご興味のある方は、ぜひご活用ください。
所定の審査により融資額は変動します。また、審査結果によっては融資できない場合があります。
支払期日前に返済する場合(一部償還を含む)は、早期返済違約金をいただきます。
法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。
本シミュレーションの結果は、本日をお借入日とした場合の参考値です。目安としてご利用ください。
まとめ
医療接遇は、単なる表面的なマナーではなく、患者の不安やストレスを軽減し適切な医療を提供するために欠かせない重要な要素です。
また、医療接遇の徹底と向上は、経営面でもメリットをもたらします。評判の向上による増患・増益やクレーム減少による生産性向上、労働時間短縮による職場環境の改善など、医療機関全体によい影響を与えることが期待できます。
「接遇マナーの5原則」(あいさつ・表情・身だしなみ・言葉遣い・態度)を徹底し、必要に応じて外部講師による研修の実施など、医療接遇の意識を高めていきましょう。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /