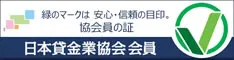- 0120-128-552 (受付時間 / 9:30~18:00)
- お申込み
- トップ
-

- 医療・介護業界の基礎知識
-

- 記事一覧
-

-
薬局の経営は厳しい?成功するために意識すべきポイントを解説
-
薬局の経営は厳しい?成功するために意識すべきポイントを解説
薬局の経営は厳しい?成功するために意識すべきポイントを解説
調剤薬局/ドラッグストア
公開日:

昨今は薬局数が増加傾向にあり、薬局経営は競争が激しくなっています。しかし、今後高齢者の増加が見込まれる人口動態を考えると、薬局が果たす役割は大きくなっていくでしょう。
この記事では、薬局の経営が厳しいといわれている理由や背景、薬局の経営を成功させるためのコツを解説します。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /
薬局の経営は儲かる?
薬局数の増加や薬剤師の人手不足などの影響もあり、昨今は薬局の経営が厳しいといわれています。
まずは、薬局の経営は儲かるのかどうか、なぜ厳しいといわれているのかを見ていきましょう。
薬局の数が増えており競争が激しくなっている
厚生労働省の資料によると、薬局薬剤師数と薬局数は増加しています。
年度
薬局数
薬局薬剤師数
平成元年
36,670
47,387
平成10年
44,085
81,220
平成20年
53,304
135,716
令和2年
60,951
188,982
薬局数の増加に伴い、薬剤師数も増加しているものの、薬剤師の需要には地域格差があり、特に地方では薬剤師が不足しています。
厚生労働省の「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、都道府県別の「人口10万人あたりの薬剤師数」を調べた結果、全国平均が190.1人に対し、沖縄県が139.4人と最も少なく、次いで福井県の152.2人、青森県の153.0人となっています。
また、全国平均を超えているのは徳島県や東京都など一部の都道府県のみで、ほとんどが全国平均を下回っています。
薬局数の増加により、薬剤師の勤務地が分散し、各店舗で必要とされる薬剤師の数が不足していることが要因と考えられます。
また、昨今は大手薬局チェーンによる薬剤師の新卒大量採用や、調剤を併設しているドラッグストアの台頭などの影響もあり、薬剤師の確保が難しくなっています。
さらに、厚生労働省の「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国に届出をしている薬剤師数のうち、 女性の割合は61.4%でした。
一般的に、女性は男性よりも家事や育児を理由に離職したり休職したりするケースが多いため、女性が多い構造も人手不足につながっていると考えられるでしょう。
薬剤師を確保するためには、相応の条件を提示して求人募集をかける必要があります。人手不足だけでなく、人件費の高騰も薬局経営を難しくしている要因です。
医療従事者の賃上げが求められている
厚生労働省保険局医療課による厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要」では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組みが求められています。
令和6年度診療報酬改定では、特例的な措置として以下のような対応が行われました。
病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種
+0.61%の改定
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者
+0.28%の改定
また、令和6年度において看護職員や病院薬剤師を含む医療関係職種の基本給を2.5%引き上げ、令和7年度に2.0%の引き上げの実現がめざされています。
今後も物価高騰や国全体で賃上げの動きが進むと、ますます人件費が高騰すると考えられるでしょう。人件費の高騰は経営を圧迫する要因の一つとなるため、より厳しさも増していくと考えられます。
医療費の削減が進められている
薬局の主な収益源となるのは、保険適用で処方された医薬品に基づく調剤報酬です。調剤技術料や薬剤料が含まれますが、昨今は医療費の削減が進められており、薬局の経営に悪影響が出ると考えられます。
日本は少子高齢化が急速に進展しており、医療費が増大し続けると、社会保険制度の維持が困難になりかねません。
特に、団塊の世代が全員75歳以上となる「2025年問題」により、医療費や介護費が急増すると予測されています。医療費の削減を図るため、政府としても医療費適正化に向けた取り組みを行っています。
厚生労働省の「第4期医療費適正化計画」においても、医療の効率的な提供をめざす一環として、重複投薬・多剤投与の適正化や薬価が低い後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進が盛り込まれています。
そのため、薬局としては、調剤報酬や薬価による収益が見込みづらくなると考えられるでしょう。実際に、「厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要」では、以下のように薬価の引き下げが行われました。
薬価
-0.97%(R6年4月1日施行)
材料価格
-0.02%(R6年6月1日施行)
一般的に、薬価が引き下げられると薬局が卸売業者から仕入れる価格と販売価格の差が縮小し、収益が減少します。人件費をはじめとしたコストの上昇に加えて収益が減少すれば、経営が厳しくなるのは致し方ありません。
調剤薬局の種類
一般的に、薬局とは処方箋を受付ける調剤薬局を指します。調剤薬局にもいくつかの種類があり、それぞれ特徴は以下のように異なります。
一般薬局・面対応薬局
- 病院から離れた場所に位置し、特定の医療機関に依存せず、複数の医療機関の処方箋を扱う薬局
- 一般用医療品や生活用品も取扱うことが多く、利便性の高さが特徴
門前薬局
- 病院の近くに位置し、その病院からの処方箋を多く受付ける薬局
- 小規模な独立薬局や大手チェーン薬局など形態はさまざま
門内薬局
- 病院の敷地内にあるが、病院が経営しているわけではない薬局
- 病院の処方箋だけでなく、他の医療機関からの処方箋を受付けることもある
院内薬局
- 患者が病院から出ることなく、直接薬を受け取れる薬局
- 高度な医療を提供する施設内で設置されることが多く、専門的な知識が求められる
薬局と一口にいっても、それぞれ特徴や求められる役割が異なります。地域のニーズや特性に応じて重要な役割を果たすことで、なくてはならない存在として薬局を経営できるでしょう。
薬局の経営を成功するために意識すべきポイント

薬局の経営を成功させるためには、利用者を増やして収益を増やす必要があります。また、昨今の医療ニーズに対応して、地域医療を支える際に重要な役割を果たすことも重要です。
以下で、薬局の経営を成功するために意識すべきポイントを解説します。
処方箋を集める
調剤薬局の収益のうち、約96%は保険調剤による調剤報酬が占めるといわれています。そのため、できるだけ処方箋を集めることは、安定的に収益を得るために欠かせません。
たとえば、地域住民のニーズに応じたサービスを提供して患者と信頼関係を築いたり、調剤業務だけでなく服薬指導や健康管理に関する相談に応じたりする対応が考えられます。
患者に寄り添った対応を心がければ、安心感を与えられ、安定的な利用者の確保に繋がり、結果的に多くの処方箋を集められる効果が期待できます。
あわせて、近隣の医療機関や福祉施設などに営業し、認知度を高めるための努力も行うとよいでしょう。
加算を確実に計上する
加算を確実に計上すれば、得られる収益を確保できます。さまざまな加算項目がありますが、後発医薬品調剤体制加算や地域支援体制加算、服薬情報等提供料など、得られる加算を確実に計上することが大切です。
なお、「令和6年度診療報酬改定の概要」では、主なポイントとして以下の3点が挙げられています。
- 地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し
- 質の高い在宅業務の推進
- かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価の見直し
政府がどのような意向を持っているのかを認識・把握すれば、効率よく加算を得られる可能性があります。今後薬局にどのような役割が求められるのかを読取り、対応を進めていきましょう。
経費をできるだけ抑える
収入を増やすことも大切ですが、薬局運営に関する経費をできるだけ抑えることも効果的です。薬局経営の経費で最も多いのは、医薬品の仕入れ費用で約70%程度、次いで人件費で約20%程度といわれています。
つまり、できるだけ安く医薬品を仕入れれば経営にゆとりが生まれるでしょう。共同購入やボランタリーチェーンなどの活用を検討し、経費を抑えましょう。
なお、人件費を抑えるための手段として、パート従業員の有効活用が考えられますが、過度に人員を削減すると1人あたりの業務負荷が増大し、就業環境が悪くなる点に注意が必要です。
オンライン服薬指導を導入する
オンライン服薬指導を導入し、サービスの利便性を高めれば利用者を増やせる可能性があります。利用者が相談しやすい環境を整備すれば、より地域医療へ貢献できるでしょう。
外出が難しい方にとって、オンラインで処方箋を受付け、服薬に関する相談ができる薬局はありがたい存在です。特に、高齢者の方が多く住んでいる地域であれば、オンライン服薬指導の需要が見込まれるでしょう。
在宅医療のニーズに対応する
政府は、できる限り住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、あんしんして自分らしい生活を実現できる社会をめざすために、「地域包括ケアシステム」を推進しています。
薬局としても、医療機関や介護事業所と連携しながら、在宅医療のニーズに対応する必要があります。地域連携を強化し、在宅医療に特化したサービスを提供すれば、薬局としての競争力を高められるでしょう。
OTC(一般用医薬品)を販売する
保険調剤だけでなく、OTC(一般用医薬品)を販売して物販収益を得れば、安定的に収益を得られる可能性があります。
また、利用者に対して服用中の薬剤とOTCとの飲み合わせをチェックできるサービスなどを提供すれば、より利便性を感じてもらえるでしょう。
OTCだけでなく、健康食品や日用品などを販売する方法もあります。大手ドラッグストアのようにさまざまな品物を取りそろえば、近隣の方々を顧客として確保できる可能性が高まります。
デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する
デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、業務を効率化すれば、薬剤師は対人業務により多くの時間を割き、良質なサービスを提供できるでしょう。
また、オンライン診療や電子処方箋を活用すれば、薬局側の業務負担を軽減できるだけでなく、患者の利便性が高まります。その結果、より多くの利用者を取り込める可能性が生まれるでしょう。
なお、令和6年度診療報酬改定において、「医療DX推進体制整備加算」が新設されました。
オンラインで診療情報・薬剤情報を確認できる体制を整備し、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを導入して質の高い医療を提供するための体制を確保している場合、4点が加算されます(月に1回)。
薬局を開業するときの流れ
実際に薬局を開局する際には、行政でさまざまな手続きを経なければなりません。以下で、薬局を開業するまでの具体的な流れを解説します。
保健所へ薬局開設許可申請書を提出する
都道府県に設置されている保健所へ、薬局開設許可申請書を提出します。薬局の平面図や事業内容書、業務体制概要書などを用意する必要があります。必要書類は、事前に保健所で確認しておくとよいでしょう。
なお、薬局には以下のようにさまざまな設備要件・人的要件が設けられています。
- 構造面積は概ね19.8平方メートル以上(事務所・更衣室・トイレを含まない)
- 明るさは薬局内60ルックス以上
- 鍵のかかる貯蔵設備を有すること
- 1日の平均処方箋数が40までである場合は薬剤師1人、40以上増えるごとにさらに1人の人員配置が必要
列挙したのはあくまでも一例で、他にもさまざまな要件が設けられています。要件をクリアしていることを確認したうえで、申請しましょう。
保健所基準調査を経て開設の許可を受ける
薬局開設の許可基準を満たしているかを確認するため、保健所の現地調査を受けます。検査を受ける時点で、基準をすべてクリアしていなければなりません。
自治体によって差がありますが、開設の許可を受けるまでに7~10日程度の時間がかかるのが一般的です。
厚生局に保険薬局指定申請書を提出し審査を受ける
保健所より薬局開設許可証が届いたら、厚生局へ保険薬局指定申請書を提出しましょう。厚生局から保険薬局の指定を受けなければ、保険薬局として認められません。
なお、保険薬局としての指定を受ける際の必要書類は以下のとおりです。
- 保険医療機関・保険薬局指定申請書
- 薬局開設許可証の写し
- 保険薬剤師の指名、保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号、担当診療科名を記載した書類
- 保険薬剤師以外の薬剤師の数を記載した書類
- 薬局の施設基準を満たしていることを示す書類(平面図、周辺図、開局時間など)
- 保険薬局の新規指定及び指定更新に係る確認書類
- 在宅医療のみを実施する医療機関の指定に係る確認様式(在宅医療のみを実施する保険医療機関の場合のみ)
- オンライン資格確認の導入計画書またはオンライン資格確認導入の猶予届出書
- 受付番号情報提供依頼書兼回答書の写し
毎月20日~25日頃に、厚生局の審査会が実施されます。審査に通過すれば保険薬局として認められ、開設できます。
行政関連の手続きと並行して、必要な医薬品や器具を揃えたり、スタッフの雇用・教育を行ったりしましょう。
出典:関東信越厚生局「【添付書類等】保険医療機関・保険薬局指定申請書関係」
調剤報酬担保ローンのご相談はAGメディカルへ
競争が激しくなっている背景もあり、薬局の経営は容易ではありません。薬局を開設したものの、資金繰りが苦しくなってしまう事態は起こり得るでしょう。
薬局の開業後、資金繰りを改善したいときはAGメディカルの「調剤報酬担保ローン」がおすすめです。
「調剤報酬担保ローン」とは、国民健康保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金の支払機関に対して有する債権を担保に、融資を受けられるサービスです※1。
融資対象者
調剤薬局事業者等
契約利率
年3.5%〜15.0%
契約額
100万円〜10億円※2
保証料・契約時手数料
不要※3
保証人・不動産担保
原則不要※4
最大で調剤報酬請求額の4.0ヶ月分の資金を調達でき、調達したお金は薬剤仕入先への支払資金や社会保険料・税金未納分の支払資金など、さまざまな用途で利用可能です。
お申込みの前に、資料請求やご相談も可能です。融資が必要なときは、お気軽にお問合せください。
審査結果によっては融資できない場合があります。
所定の審査により融資額は変動します。
支払期日前に返済する場合(一部償還を含む)は、早期返済違約金をいただきます。
法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。
まとめ
薬局経営の厳しさは増しているいっぽうで、今後高齢者人口が増加し、地域医療において薬局が果たす役割は大きくなっていると考えられます。
処方箋を多く集めるための工夫をしたり、国が進めている在宅医療へのニーズに対応したりすれば、競争力を高められます。また、オンライン服薬指導を導入したりデジタルトランスフォーメーション化の推進を検討したりすると、収益性を向上できるでしょう。
薬局経営を始めたあと、資金繰りで苦しくなってしまう場面があるかもしれません。支払いサイトの関係で融資を受けたい場合は、ぜひAGメディカルの「調剤報酬担保ローン」の活用をご検討ください。
WEBで24時間お申込み可能で、お電話でもご相談いただけるため、お気軽にお問合わせください。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /