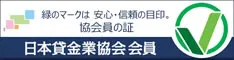- 0120-128-552 (受付時間 / 9:30~18:00)
- お申込み
- トップ
-

- 医療・介護業界の基礎知識
-

- 記事一覧
-

-
介護施設(老人ホーム)経営は難しい?必要な資格や費用を解説
-
介護施設(老人ホーム)経営は難しい?必要な資格や費用を解説
介護施設(老人ホーム)経営は難しい?必要な資格や費用を解説
介護施設/訪問介護
公開日:

日本では少子高齢化が進行しており、今後高齢者の人口はますます増えていくでしょう。介護施設の需要は高まると考えられ、介護施設の経営を検討している方もいるのではないでしょうか。
介護施設の経営は需要増加に対応できる反面、初期投資額を用意する必要があったり、安定的に収益を得るのが難しかったりするデメリットがあります。
介護施設の経営を成功させるためには、経営が難しいといわれている背景や、ビジネスモデルを理解することが欠かせません。
今回は、介護施設を経営する難しさや経営にあたって必要な資格、費用などを解説します。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /

もくじ
介護施設経営の現状は?
高齢化社会の進展により、介護施設の需要は増加しています。しかし、厚生労働省の資料を見ると、介護施設の経営状況はあまり芳しくないのが実情です。
まずは、データを交えながら介護施設経営の現状について解説します。
介護施設の収支差率(利益率)
厚生労働省の「令和5年度介護事業経営実態調査結果の概要」によると、介護老人福祉施設の平均収支差率はマイナス1.0%(税引前)でした。
収支差率とは、一般的な企業では営業利益率にあたり、売上に対してどれくらいの利益が出ているかを図る指標です。「(介護サービスの収益額-介護サービスの費用額)÷介護サービスの収益額」で計算します。
収支差率がマイナスだと、経営が赤字であることを意味します。つまり、令和5年度における介護老人福祉施設の収益率は、平均で赤字であったということになります。
介護サービス全体の収支差率は悪化傾向にあり、介護施設の経営はかんたんではありません。昨今は物価や人件費の上昇が経営を圧迫し、収支差率に悪影響を与えていると考えられます。
介護施設の倒産件数
株式会社東京商工リサーチによると、2024年における「介護事業者(老人福祉・介護事業)」の倒産件数は、過去最多の172件(前年比40.9%増)でした。
人手不足や競合の増加による収益性の悪化など、倒産に至る理由はさまざまです。高齢者人口の増加に伴って介護施設の需要は高まっている中で、倒産件数は増加しているため、介護施設の経営は難しいことがわかります。
また、介護業界の人手不足は深刻です。厚生労働省の「令和4年版 厚生労働白書」によると、令和3年度における介護関係職種の有効求人倍率は3.65倍でした(全職種では1.03倍)。
人手不足の解消だけでなく、物価高の中で多様化するニーズに対応しなければならないため、介護施設の運営者にはさまざまな工夫が求められるでしょう。
介護施設の経営が難しい理由

統計上、介護事業者の倒産件数が増えていることからも、介護施設の経営は難しいことがわかります。
なぜ介護施設の経営が難しいのか、具体的な背景や理由を見ていきましょう。
利益率が低いビジネスモデルである
介護施設は利益率が低いビジネスモデルであるため、経営が難しいといわれています。
介護施設の主な収入源は介護報酬です。介護サービスを提供したとき、利用者からは費用の1割(一定以上所得者の場合は2割~3割)を受取り、残りの7割~9割は国から受取ります。
介護報酬は、地域ごとの人件費やサービス提供体制などを考慮して、政府が価格を定めています(公定価格)。そのため、ご自身で独自のサービスを提供し、独自の料金体系を設定することはできません(保険外サービスを除く)。
また、介護報酬は3年ごとに改正されるため、収益を安定させることが難しく、受取れる介護報酬で人件費や光熱費などのランニングコストをカバーできないと、慢性的な赤字になってしまいます。
入居一時金や保険外サービスの利用料などを増額し、収益を増やすことは可能です。しかし、競合よりも高い価格設定をすると、利用者を確保できなかったり利用者離れが発生してしまったりなど問題が発生するでしょう。
人材確保が難しい
介護業界は人手不足が慢性化しており、十分なサービスを提供するための人材確保が難しい状況にあります。
昨今は介護ロボットや見守りロボットなどが登場しているものの、やはり介護の現場では人手が必要です。介護は身体介護や力仕事が多く体力的に負担となる点や、夜勤がある点が敬遠されやすく、そもそも介護職を希望する求職者はあまり多くありません。
また、介護施設が得られる介護報酬は限られています。人を集められるだけの魅力的な待遇を用意することも難しいのが実情です。
人手不足が深刻化すると、サービスの低下や就業環境の悪化などの悪循環につながり、利用者離れが発生する事態にもなりかねません。
さらに、採用した人材の管理も重要です。職場での人間関係が原因で、せっかく確保した人材が離れてしまうこともあります。
競合が増え利用者の確保が難しい
昨今は高齢者を対象としたサービスの需要が増えていることもあり、社会福祉法人をはじめ、民間企業も介護業界に参入しています。競合が増えて利用者を獲得するための競争が激化している点も、介護施設の経営が難しくなっている一因です。
また、介護施設が提供するサービスはどうしても似通ってきます。生活介助やレクリエーションなどが提供するサービスの軸になるため、差別化には限界があります。
さらに、介護報酬は公定価格で決まっているため、差別化を意識し、サービスの質を高めすぎてコスト増加につながると本末転倒です。
利用者の確保につなげるための訴求が難しいのが現実であり、思うように利用者を確保できず、経営状況が悪化してしまう施設が多いと考えられるでしょう。
介護施設(老人ホーム)の種類
介護施設といっても、以下のように施設の種類はさまざまです。
- 老人ホーム
- デイサービス
- 訪問介護事業所
- デイケア施設
- グループホーム
- ケアハウス
どのような施設を経営するかによって、適している立地や初期投資額などが異なります。以下で、老人ホームに特化して種類や特徴を紹介します。
老人ホームの種類
民間企業が開設できる老人ホームは「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の3種類です。
介護付き有料老人ホーム
介護が必要な高齢者向けの居住施設で、介護サービスを提供する
住宅型有料老人ホーム
生活支援サービスが付いた高齢者施設で、介護が必要な場合は外部の訪問介護などを利用する
健康型有料老人ホーム
自立した生活が可能な高齢者向けの施設で、介護が必要になった場合は退去しなければならないケースがある
介護付き有料老人ホームは、介護サービス付きの高齢者向け居住施設で、主に「介護専用型」「混合型」に分けられます。
要介護度によって入居対象者やサービス内容が異なり、「介護専用型」は主に要介護認定を受けた方、「混合型」は要支援・要介護のどちらの方でも入居できます。
住宅型有料老人ホームは、生活支援に関するサービス付きの高齢者向け居住施設で、自宅に住んでいる感覚で生活できる点が特徴です。
要介護度が低い自立した高齢者向けで、必要に応じて介護サービスを受けたい場合は、外部の介護サービスを利用しながら生活できます。
健康型有料老人ホームは、介護が必要ない自立度の高い高齢者向けの老人ホームです。食事をはじめとしたサービスが付いているものの、介護が不要な人向けの施設であるため、介護が必要になった場合は退去しなくてはならないのが一般的です。
介護施設(老人ホーム)の経営をはじめるために必要な資格
介護施設を開業するにあたって、特別な資格は不要です。経営者自身が介護関連の資格を保有していなくても、介護施設の経営をはじめられます。
ただし、介護保険サービスを提供するためには、自治体から「介護事業者」としての「指定」を受ける必要があります。たとえば、東京都では以下のような流れで指定を受けなければなりません。
- ①事業所開設予定月の4ヶ月前までに新規指定前研修に申込む
- ②事業所開設予定月の3ヶ月前までに新規指定前研修を受講する
- ③指定予定日の2ヶ月前の15日までに申請書を提出する
- ④指定申請書の審査を受ける
- ⑤指定介護サービス事業所として指定を受ける
指定前研修への申込み時点で、法人において事業所開設の具体的な予定があることが求められます。また、研修は申請する事業所の管理者や法人代表者になる予定の方が参加しなければなりません。
なお、経営する介護施設が特別養護老人ホームの場合、施設長は以下の資格要件を満たさなければなりません。
- 社会福祉主事の要件を満たす者
- 社会福祉事業に2年以上従事した者
- 社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者
ほかにも、訪問介護のサービスを提供する場合は、介護福祉士・介護福祉士実務者研修などの資格を保有するサービス提供責任者を置く必要があります。
介護施設(老人ホーム)の経営をはじめるときに必要な初期費用
実際に介護施設を経営する際には、まとまった初期投資が必要となります。経営する施設の規模や立地によって必要な費用は異なるものの、必要な初期費用の目安をまとめました。
デイサービス
総額1,000万円程度(物件取得費・内装工事費・設備費・送迎用車両費・広告宣伝費など)
老人ホーム
総額1億円を超えることもある(土地購入・建物の建築費・設備費・備品購入費・広告宣伝費など)
いずれの施設を経営する場合でも、必要な初期費用額は、施設の立地・営業形態・規模によって大きく変動します。
たとえば、デイサービス施設を新規で開設する場合は、物件取得費や内装工事費が高額になりやすいでしょう。いっぽうで、居抜き物件や一戸建ての民家を利用すれば、初期費用を抑えられます。
老人ホームに関しても、土地を新規で取得するのか、既存の建物を使用するのかなどによって費用は変わります。自己資金だけで初期費用を用意できない場合は、国や自治体が行う助成金・補助金を利用したり、融資を受けたりすることを検討しましょう。
介護施設(老人ホーム)の経営を成功させるコツ
介護施設の経営は難しい面があるいっぽうで、さまざまな工夫を施せば経営を成功させることが可能です。
加算をきちんと計上したり、IT・ICT活用で業務を効率化したりして、「収入を増やす」「経費を減らす」対策を実践しましょう。
加算を確実に計上する
加算をきちんと計上すれば、介護報酬を正確に受取れます。また、介護報酬の加算を把握したうえで、どのようなサービスを提供できるか検討しましょう。
「令和6年度介護報酬改定」において、居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件や市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合など、新たな加算が設けられました。
介護報酬は、介護に関する状況の変化に応じて3年に1度見直されます。改定情報を収集し、変更点や新たな加算要件を正確に理解しましょう。
IT・ICT活用で業務を効率化する
ITやICTの活用により業務の一部を自動化できれば、業務の効率化と省人化を実現できます。これにより人件費を抑えられ、収支差率が改善する可能性が考えられるでしょう。
たとえば、見守りセンサー(見守りカメラ)や介護ロボットなどを活用すれば、スタッフの身体的・精神的負担を軽減できます。また、日々の記録や報告書をITツールに移行することで、業務時間を削減できるでしょう。
業務の効率化により、スタッフは対人サービスにリソースを割けるようになるため、提供できるサービスの質が向上します。結果的に利用者の満足度を高められ、得られる収益を増やせる可能性があります。
保険外サービスを提供する
介護保険ではカバーされない保険外のサービスを提供すれば、収益性を高められます。たとえば、配食サービス・家事代行・ペットの世話・買い物支援などのサービスを提供し、介護報酬とは別の収益源を確保する方法が考えられるでしょう。
また、保険外サービスは公定価格ではないため、利用料金は事業者が自由に設定できます。独自のサービスを用意することで利用者のニーズを満たし、収益増加につなげられるでしょう。
幅広い保険外サービスを用意すれば、介護保険サービスだけでは対応できない多様なニーズに応えられます。設備投資や人材確保などのハードルはありますが、可能な範囲でサービスのメニューを増やすとよいでしょう。
融資を受ける際はAGメディカルの「介護報酬担保ローン」がおすすめ
介護施設経営するにあたり、資金調達をしたいときはAGメディカルの「介護報酬担保ローン」がおすすめです。介護報酬担保ローンとは、国民健康保険団体連合会(国保)に対して有する債権を担保にとして提供し、融資を受けるサービスです。
最大で介護給付費の4.0ヶ月分の資金、金額にして100万円から最高10億円までのご融資に対応しています※1。ファクタリングをご利用中・赤字決算でもご検討可能で、一時的に資金繰りが苦しい状況でもお申込みいただけます。
なお、調達したお金の利用目的は事業資金としてであれば自由で、事業投資だけでなく各種税金・社会保険料のお支払いにも利用可能です。保証料・契約時手数料は不要、保証人・不動産担保も原則不要で、WEBから24時間お申込みいただけます※2※3。
所定の審査により融資額は変動します。また、審査結果によっては融資できない場合があります。
支払期日前に返済する場合(一部償還を含む)は、早期返済違約金をいただきます。
法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。
まとめ
介護施設の経営は難しい面があるものの、高齢者が増加すると見込まれる状況において、安定して収入を得られる可能性があります。
競合との差別化を図ったり、ITやICT化を通じて働きやすい職場環境を整備したりすれば、利用者の満足度を高められるでしょう。
介護施設は利益率が低く、また競合が増えている関係で、利用者の確保が難しいという特徴があります。これらのハードルを乗り越えて、安定的に介護施設を経営しましょう。
なお、介護施設の経営をはじめたあとに、事業投資資金を用意したり、一時的に運転資金の借入れが必要になったりすることがあるかもしれません。
融資を受けたい場合は、保証料・契約時手数料が不要でお申込みやすい、AGメディカルの「介護報酬担保ローン」の利用をご検討ください。
\ 24時間受付中!最大10億円まで融資可能 /